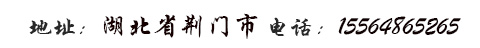曼珠沙華
|
曼珠沙華は、紅い花が群生して、列をなして咲くことが多いので特に具合の好いものである。一体この花は、青い葉が無くて、茎のうえにずぼりと紅い特有の花を付けているので、渋味とか寂びとか幽玄とかいう、一部の日本人の好尚からいうと合わないところがある。そういう趣味からいうと、蔟生している青い葉の中から、見えるか見えないくらいにあの紅い花を咲かせたいのであろうが、あの花はそんなことはせずに、冬から春にかけて青々としてあった葉を無くしてしまい、直接法に無遠慮にあの紅い花を咲かせている。そういう点が私にはいかにも愛らしい。勿体ぶりの完成でなくて、不得要領のうちに強い色を映出しているのは、寧ろ異国的であると謂うことも出来る。秋の彼岸に近づくと、日の光が地に沁み込むように寂しずかになって来る。この花はそのころに一番美しい。彼岸花という名のあるのはそのためである。 この花は、死人花しびとばな、地獄花じごくばなとも云って軽蔑されていたが、それは日本人の完成的趣味に合わないためであっただろう。正岡子規などでも、曼珠沙華を取扱った初期の俳句は皆そういう概念に囚われていたが、 苡ずずだまの小道尽きたり曼珠沙華 子規 晩年にはこの句位くいに到達して居る。これは子規は偉かったからである。 市電が三宅坂から御濠に沿うて警視庁の方に走ると、直線と曲線とのよく調和した御濠の緑色土手に曼珠沙華がもう群がり咲いているのが見える。そして青くしずまり返った御濠の水には、鵜が一羽黄いろい首をのばして飛んでいたりするのが見える。この新鮮な近代的交錯は、藤原奈良の歌人も、元禄の俳人もついに知らずにしまった佳境である。 底本:「日本の名随筆1 花」作品社 (昭和58)年2月25日第1刷発行 (平成13)年3月20日第29刷発行底本の親本:「齋藤茂吉全集 第六巻」岩波書店 (昭和49)年5月初版発行青空文庫作成 预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇 |
转载请注明地址:http://www.shisuana.com/ssjb/8426.html
- 上一篇文章: 桂花秋风袭来,金桂飘香
- 下一篇文章: 玩转南京美丽乡村全攻略来啦